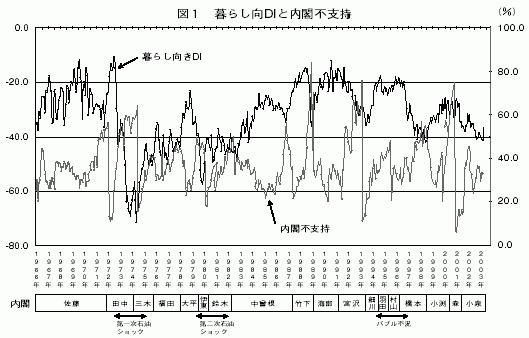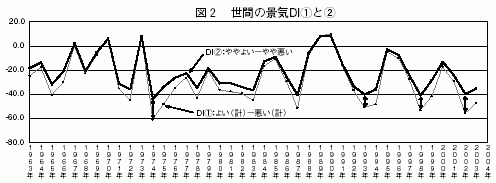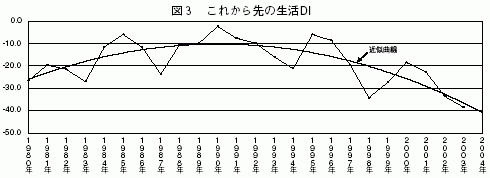時事世論調査から見た景気動向指数
時事通信社・中央調査社では、景気と暮らし向きに関する意識調査を長期間継続して行っている。現在の設問は、「暮らし向き」、「物価」、「世間の景気」、「これから先の生活」の4問で、「暮らし向き」、「物価」、「世間の景気」の3問は1960年代前半から、そして「これから先の生活」についての設問は1980年5月から毎月行われている。これらは、いずれも尺度型の選択肢により暮らしについての意識を把握することを目的としているが、そのデータからDI(DiffusionIndex)を用いることにより、月次の動向に加えて長期の方向感も把握することが出来る。
DIは景気動向指数を指し、「良くなった」から「悪くなった」を引いた数値を指数として景気の拡張と収縮の転換点、つまり景気の方向感を捉えるために使われているが、景気と関係の深い指標についても同様の把握が可能である。DIの算出方法は、内閣府の景気動向指数のように、それぞれの経済指標(季節変動後調整数値)が3ヶ月前に比べてプラスになった指標の系列数を全系列数で割り、パーセント表示したものもあるが、本稿では、「よい」、「(暮らし向きが)楽になった」など肯定的評価の小計のパーセント表示から、「悪い」「苦しくなった」などの否定的評価を差し引いた数値を算出する簡便な計算方法を用いている。最も長いもので40年にわたる月次データを紹介し、概観することが、小稿の目的である。
1.「暮らし向き」DIの概観
暮らし向きの設問は、1963年12月から開始し、当初は選択肢が「楽になった」、「変わりない」、「苦しくなった」だった。1966年6月から、「大変楽になった」、「やや楽になった」、「変わりない」、「やや苦しくなった」「大変苦しくなった」の5点尺度となった。この設問のDIは常にマイナスで、そのマイナスの度合いによりその時々の変化、傾向をみる事になる。
(図1)をみてみると、調査が始まった1966年6月から、数値は緩やかに上昇していくが、1972年のオイルショックを契機に1973年に入ってから急速に数値が悪化し、1974年10月に-71.7の歴代最低値を記録するまで低迷した。その後、1979年から1980年にかけて一時数値が悪化したものの、全般に上昇基調で推移している。
バブル崩壊の年、1989年4月から7月にかけて、それまでのマイナス10%台からマイナス30%台への下落が見られるが、それ以降1992年あたりまで相対的に高いマイナス10%から20%台で推移していることを考えると、これらがバブル崩壊によるものと考えるべきではないだろうi。
「失われた10年」といわれる90年台から現在までを見てみると、80年代までに比べ、相対的に上昇と下落の振幅が狭くなっているように見られる。全般的に高止まりしている数値が、1998年ごろからは下落傾向にあるものの、それでも70年代や80年代初頭に見られるような大幅な下落とはなっていない。景気の変動とは別に生活水準の相対的な向上が実感されているためであろう。
加えて、オイルショックやトイレットぺーパー買占め騒動(1973年11月)のように、自分たちの生活に直接影響が出る出来事と、バブル崩壊という日常からややかけ離れた出来事は、人々に与える心理的影響の度合いが異なり、生活に密着した出来事の影響がバブル崩壊の影響を上回ったともいえるかもしれない。
暮らし向きのDIを、1960年6月から毎月実施している内閣支持率と比較可能と思われるものを取り出して、どのような関係があるかを検討してみたい。内閣支持率は、時の内閣に対して一般市民の「支持」、「不支持」、「わからない」によって数値化されている。暮らし向きのDIと内閣の不支持をプロットして関係をみたところ、(図1)のようになった。
内閣の不支持率は、新しい内閣が発足すると前の政権末期に比べて大幅に減少するが、その後緩やかに上昇していく傾向をたどっている。
対して暮らし向きのDIは、内閣不支持が増加に転じるときにマイナスの度合いが増加に転じている。回帰分析など詳細は別の機会に譲りたいが、景気の転換点としてのDIと内閣不支持の関係を今後も注視したい。
i 日本国内では、89年4月にリクルート事件により竹下内閣が退陣。
中国では天安門事件の発生から収束までの期間とほぼ重なる。
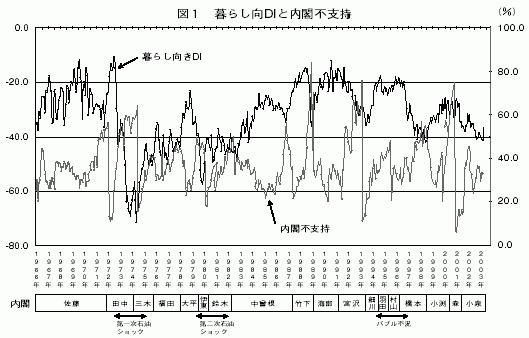
2.「物価」DIの概観
次に物価についてのDIを見てみよう。物価DIは、1961年2月から調査開始と、設問中最も古くからのデータがある。物価についての選択肢は「落ち着いた」、「上がる」、「下がる」の3点尺度である。「上がる」から「下がる」を差し引いたものをDIとしている。物価の設問は、暮らし向きの設問と異なり、DIはおおむねプラスの値を推移している。高度成長期からバブル期まで、世の中は基本的にインフレ傾向であることを、これらの数値が長い間示してきたといえる。
ところが、90年代後半からのデフレによる不況の深刻化・長期化がDIの数値を低下させ、2001年5月には初めてマイナスの数値を記録し、2002年4月まで丸一年間マイナスが継続した。それ以降今に至るまでは、プラスの数値となっている。
この設問では、「落ち着いた」の回答の分布に特徴が見られる。設問開始以来、「落ち着いた」の回答は概して少なく、「61年2月から72年12月(オイルショック)まで」、「73年から90年末(バブル崩壊)まで」、「91年から現在(平成不況)まで」に分けて各回答の移動平均を取ってみると(表1)、それぞれ8.1、13.3、27.5であった。
平成不況期に入ると、「上がる」以外のすべての回答が増加したためDIの数値は大幅に減少している。「上がる」以外の回答で増加が最も顕著なのは「落ち着いた」である。この結果からは、DIの数値が減少しているのは、物価が「下がる」と回答した人が増えたというよりも、物価が「上がる」と答えた人が減り、「落ち着いた」と答えた人が増えたことに原因があると思われる。

3.「世間の景気」DIの概観
世間の景気は、1963年1月から調査を開始し、「暮らし向き」同様に5点尺度で、選択肢は「たしかによくなってきた」から「たしかに悪くなってきた」までの5択である。暮らし向きDIと比較してみると、全般的に数値は上方に位置している。
世間の景気DIは、「たしかによくなってきた」と「ややよくなってきた」を足し合わせた数値から「やや悪くなってきた」と「たしかに悪くなってきた」を足し合わせた数値を引いて算出しているが、このDI①と「ややよくなってきた」から「やや悪くなってきた」を引いたDI②をプロットしてみると(図2)のようになった。
これら2つのDIはほぼ同じ軌跡をたどっているが、DIのマイナスの度合いが大きくなると、DI①の方がDI②よりもよりマイナスの方に位置するようになっている。積極的に「(世間の景気が)たしかによくなってきた」と回答する人は(実際に景気がよいと感じられても)ほとんどいないが、実際景気が悪いと感じられるときには「たしかに悪くなってきた」と回答する人が一定数存在するためであろう。
DI①とDI②の差が10以上拡がっている時期についてみてみると、1964年12月から65年7月にかけては、日本特殊鋼の倒産(64年12月)や山一證券に対する日銀特融(65年5月)、73年の12月から75年の3月にかけては、トイレットペーパーパニック(73年12月)や田中内閣総辞職(74年12月)など景気が悪いときに差が拡大しているようにみられる。しかし、バブル末期の87年1月(-10.6)と3月(-11.2)の場合は、2月に公定歩合が戦後最低(当時)の2.5%に引き下げられ、中曽根内閣が売上税法案を国会に提出したことなど、先行きの景気不安感増大により差が拡大している時期もある。なお、同じ2月にはNTT株が上場されるなど、世間一般にはバブル真っ盛りという時期でもあり、複合的な要因が考えられる。
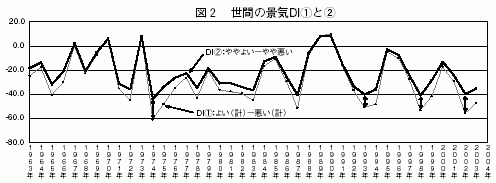
BR>
4.「これから先の生活」DIの概観
1980年5月より調査が始まった「これから先の生活」は、選択肢は、「よくなっていく」、「変わりない」、「悪くなっていく」の3点尺度で、「よくなっていく」から「悪くなっていく」を引いたものをDIとして数値を算出している。これについては(図3)のようになった。
DIの傾向からは、「悪くなっていく」が全般的に増加傾向にあるが、これは「よくなっていく」の数値に大きな変動が無いため、「変わりない」の減少と関係しているといえる。
DIの推移にあわせてプロットした近似曲線をみてみると、バブル崩壊の90年ころを頂点としてその後は減少傾向を示し、特に97年以降は調査開始時点よりも全体として低下している。この傾向のまま将来を予測すれば、ひたすら減少傾向をたどることになるが、日本経済の再成長への転換点を探る指標となるかもしれない。
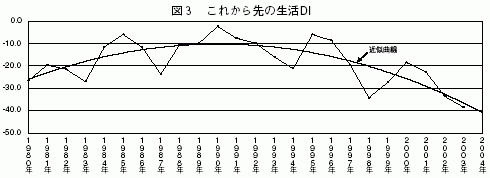
5.おわりに
それぞれの項目は、DIとしてそれ独自で景気の転換点を把握するのに役立つ上に、様々な景気関連指標との分析軸として興味深い分析が可能である。
この貴重なデータを資産として、引き続きデータの蓄積を見守っていきたい。
(調査部 木庭 雄一)
|