|
■ タバコと世論
鳥取大学医学部環境予防医学分野 尾崎米厚
世論にはさまざまな定義がある。たとえば、世論とは世論調査の方法によって明らかにされたある対象群のある時点における問題群に対する意見の構造分布であるといわれることがある。ここでは、単に「大勢の人々によって支持されている意見、考え方」という意味のみならず行政施策を円滑に進めていく場合「その意見や考え方が社会的に無視できないもの」という意味も含める。いいかえれば、政策を実施していく上で配慮しなければならない大衆の意見であるが、世論は必ずしも正しいわけではない。正しいためには、大衆がその問題について関心を持ち、その問題について十分な情報を得ており、さらに合理的な判断を下す能力を持っている必要がある。いずれにせよ、現代社会では世論は政治を動かす大きな力となっていることは事実である。
現代は、タバコ対策が流行している。医学的問題のみならず、社会的問題として多くの国民の関心事になっている。これは、2001年に厚生労働省が21世紀の国民の健康づくり運動を提唱し、その中の柱にタバコ対策を位置づけ、2003年に受動喫煙防止を盛り込んだ健康増進法という法律が施行され、2005年2月末にはWHO(世界保健機関)により提案され、ほとんどの国々により批准されたタバコ規制枠組み条約がわが国でも発効したなかで、より大きな動きになってきた。それに伴う対策も進みつつあるが、どのような対策を展開するかは、国民のタバコ問題についての世論が大きな要因となる。世論は同じような調査方法、調査項目で年余にわたり、継続的にモニタリングしていくことに意味があるが、特にそれが問題になる前からの情報を把握することは困難である。時事通信社では、1983年より継続的にタバコについての世論を調べ続けている。このような貴重なデータを分析して、示すことはわが国のタバコ対策の推進に対して、きわめて有用である。
ここでは、時事通信社により調査されてきたタバコについて、時系列に分析した。一部、考察には総理府による1989年の調査結果も利用した。
1)国民の喫煙状況の認識
タバコについての世論調査は1983年以来17回にわたり時事通信社により実施されてきている。これがタバコに関する世論の年次推移をみることができる唯一のデータである。
それによると回答者自身の喫煙行動についてはわずかな変化が認められる。すなわち、男女計でみた「吸わない」人の割合が増加傾向にある。喫煙本数も30本以上吸う者の割合がわずかに減少傾向にある(表1)。
これは、同時期に行われた日本タバコ産業株式会社による全国タバコ喫煙者率調査の結果とほぼ同様であった。調査時喫煙者でなかった人が以前習慣的に喫煙をしていたかどうかという問いについても、「過去の喫煙あり」の割合が増加傾向にあり、禁煙者の増加を意味している。
喫煙者の禁煙の意思は、年によって増減があるが、大きな傾向を見ると「いずれはやめる」人の割合が増加し、「やめない」「本数を減らす」人の割合が減少し、2003年には、「やめない」と「いずれやめる」が逆転したが、2004年には再び「やめない」方が多くなった(表1)。このように、喫煙しない人が増加し、喫煙者の中にもやめたい人が増加しているので、喫煙しない人の意見を重視したタバコ対策はますます受け入れられる余地が増大している。
1998年の調査では、喫煙者数が増えたかどうかという質問を行い、「減った」と回答したものの割合が最も高かった。女性の喫煙が増えたかどうか、未成年の喫煙が増えたかどうかの質問では大多数(前者84%、後者74%)が「増えた」と回答していた。またマナーのよい人の数は「変わらない」、タバコの宣伝は「減った」と回答したものの割合が高かった。同じ質問を1999年にも実施しているが、傾向は1998年とほぼ同様であったが、タバコの宣伝が「減った」と回答したものの割合がやや増加した(表5)。
このように女性の喫煙と未成年者の喫煙が増加していると認識している国民が多いことがわかったので、特に未成年への喫煙防止対策の重要性にはかなりの支持が得られるのではないかと考えられる。
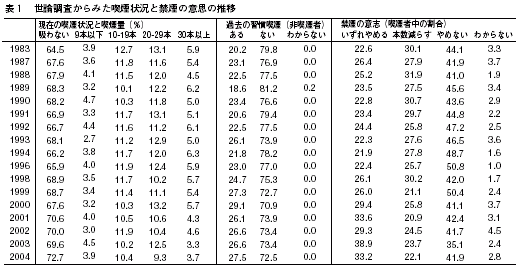
2)公共の場などにおける禁煙・分煙についての世論
時事通信社調査によると、他人の喫煙の迷惑を感じている人は、1980年代より一貫して増加傾向にある。他人の喫煙を迷惑と感じる場所は、「列車やバス」、「病院・保健所」が多かったが、1990年代より急激に減少傾向にある。現在は、「食堂や喫茶店」、「駅や停留所」、「街頭」と回答するものの割合が高く、受動喫煙対策の進展を反映した結果となっている(表2)。したがって、これらの場所での受動喫煙対策を国民も望むようになってきたといえる。
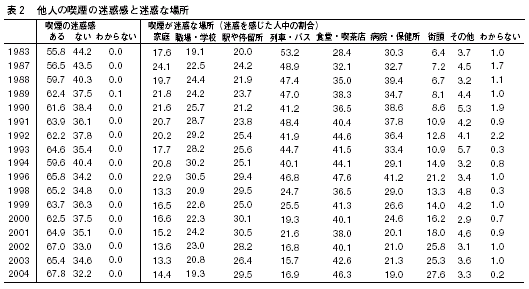
禁煙すべき場所についての意見は1996年までしか聞いていないが、「病院や保健所」が最も多く、ついで「列車・バス」、「食堂・喫茶店」、「職場や学校」であった。「食堂・喫茶店」、「駅やバス停」、「街頭」と回答したものの割合は増加傾向にある。公共の施設での禁煙法制定への賛否を尋ねると、1980年代は賛成反対派ほぼ半々で「どちらともいえない」と回答したものの割合が最も高かったが、1992年より賛成の割合が高くなり「どちらともいえない」とする割合より高くなった(表3)。
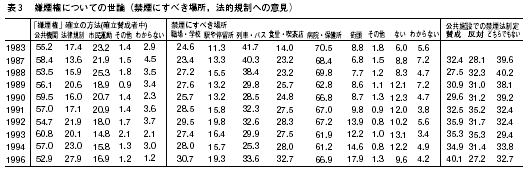
1989年に実施された健康と喫煙問題に関する総理府調査によると、喫煙者の方が他人の喫煙を迷惑に感じている割合が少なく、あまり健康に注意を払っていない人の場合も迷惑に感じる割合が少なかった。この調査によると迷惑に感じる内容は、「タバコの煙やにおい」が最も多かったが、ついで「健康や出産への影響」、「肺がんなど病気の心配」、「火事の恐れ」、「衣服や畳などに焼け焦げの心配」があげられた。またこの調査は、喫煙場所を制限すべきかどうかをたずねており、喫煙者や喫煙の迷惑感のあまりない人では賛成するものの割合が低いが、総数では過半数が制限すべきであると回答していた。この調査では、制限すべき場所は、「病院・診療所」、「公共交通機関」、「学校」、「道路」、「役所や銀行の窓口」、「飲食店」があげられており、前述の時事通信社調査の結果と同様であった。
1989年の総理府調査も1983年以降の時事通信社調査も一貫していえるのは、国民の多くの割合が他人の喫煙に迷惑を感じており様々な場所での禁煙を望んでいることであった。まだ過半数ではないが、それらを法的規制で制限しようとするものの割合が増加しており、公共施設での禁煙を推進することに合意が得られつつあるといえる。これは健康増進法成立の後押しするような社会的要望があったことを物語る。
嫌煙権とは、受動喫煙の害に着目し、非喫煙者の健康を守るために、公共の場所や共有の生活空間での喫煙規制を訴える権利主張のことで、わが国では1978年に登場した言葉である。嫌煙権という言葉を知っている割合は1983年以降7割前後であり、以前よりあまり変化がない。嫌煙権についての態度をみると、「各人の常識に任せればよい」と考えるものの割合が最も高く、年次推移をみてもあまり変化がない。「早急に実現すべき」とする者の割合は毎年およそ15%前後である。嫌煙権の確立を「したほうがよい」とする者と「必要がない」とする者の割合はほぼ半々である。その割合は1983年以降あまり変化が認められない(表4)。
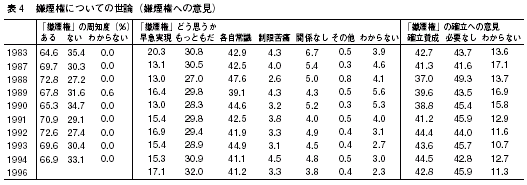
確立させたほうがよいと考える者にその方法をたずねると「公共機関の呼びかけ」がよいとする者の割合が最も多く、次いで、「法的規制」、「市民運動」であった。「法的規制」と回答したものの割合は徐々に増加している傾向にある。
嫌煙権という言葉の定着度や実現への態度はさほど進展がみられない。これは公共施設での禁煙に対する意見と比較して対照的である。これは、この言葉が一般にあまり使われなくなってきているためであろうが、1994年を最後に時事通信社調査でも調べられなくなった。
3)タバコの広告規制についての世論
1989年の健康と喫煙問題に関する総理府調査によると、当時はまだテレビのタバコの広告は行われていたにもかかわらず、テレビ広告は多いと思わないという回答が過半数であった。テレビ広告の影響については、「未成年者の喫煙を誘う」という回答が最も多く、ついで「特に影響があるとは思わない」、「健康に悪くないと思わせる」、「吸わない人の喫煙を誘う」、「禁煙の意思の妨げになる」が続いた。テレビ広告についての賛否では、「今のままでよい」とするものの割合が最も高く、「改めたほうがよい」とするのは3割であった。今のままでよいとする理由は、「吸うかどうかは個人の問題である」、「商品の広告は自由」、「タバコの広告に関心がない」であった。テレビの広告の改め方については、「喫煙と健康との関係についての注意を促す」、「未成年者に喫煙を誘うような内容を改める」、「放送の頻度をへらす」、「吸わない人への配慮を強調する」、「放送時間帯を制限する」などであった。
タバコの広告についての関心はあまり高くなかった。現在はタバコのテレビ広告は既に自主規制により中止されており、雑誌や新聞が広告媒体の中心になっているため一般市民の目に触れる機会が減り、広告規制に関する関心はさらに低下している可能性が考えられる。
4)喫煙マナーについての世論
総理府調査によると、喫煙者が喫煙するときの配慮で最も多かったのは、「混雑している場所では吸わない」であった。ついで、「子どもや病人の前では吸わない」、「公共の場所では吸わない」、「食事のときは吸わない」であった。男性に比して女性の喫煙者はより「公共の場所で吸わない」、「食事のときは吸わない」、「相手の了解を得る」、「職場ではなるべく吸わない」傾向があった。
吸わない人への配慮に関する態度では、喫煙者でも「近くで吸うべきではない」「了解を得るなど配慮をすればよい」といった回答をするものが多く、何らかの配慮をすべきであるとの意見が2/3を超えていた。喫煙の迷惑感がよくあると回答した者ではその割合がさらに高かった。
16年前のデータではあるが、喫煙者の多くが、非喫煙者になんらかの配慮をすべきであると考えており、喫煙マナーの徹底には大部分の賛同が得られると考えられる。
5)喫煙対策についての世論
総理府調査では、タバコ対策に関する要望として、「タバコの健康に及ぼす影響についての情報提供」が最も多く、ついで「自動販売機の規制」、「喫煙場所の制限」、「禁煙方法の普及」、「広告の規制」等が続いた。
1998年の時事通信社調査ではタバコの値上げについての意見を尋ねた。「賛成」と「反対」がほぼ半々であった。反対者の割合は喫煙者割合に近かった。1999年の世論調査では国際線の全面禁煙への是非をたずねたが、「賛成」が最も多かった。「どちらかといえば賛成」を含めると6割を超すため、かなりの国民に支持されているのが明らかになった(表5)。
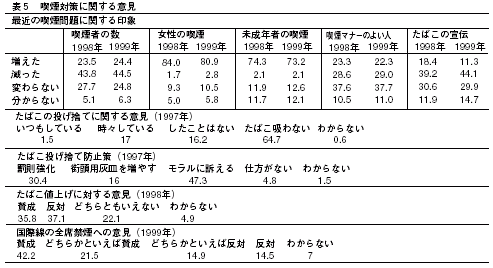
1999年に厚生省により実施された喫煙行動に関する全国調査では、喫煙対策の要望を調査しており、男性では「未成年者の喫煙防止対策」、「駅・病院などでの喫煙規制」、「学校での喫煙教育」、「タバコ税を喫煙対策にまわす」、「職場での喫煙規制」、「タバコと健康に関する情報提供」、「歩行中の喫煙規制」の順に要望が多かった。女性では、「駅・病院での喫煙規制」、「未成年者の喫煙防止対策」、「職場の喫煙規制」、「歩行中の喫煙規制」、「学校での喫煙教育」、「情報提供」、「タバコ税を喫煙対策にまわす」の順に要望が多かった。特に女性ではほとんどの項目が過半数の支持を得ていた。
従って、喫煙対策の推進はほとんどの国民が賛同しており、特に未成年者に吸わせないようにする取り組みや、公共の場所や職場での喫煙規制等は支持が高く、さらなる積極的な対策の推進の根拠となろう。さらに歩行中の喫煙の規制などは近年関心が高まっており何らかの規制を行うことも支持されると考えられる。これが一部自治体で条例化された路上の歩行中喫煙の防止策につながっているといえる。
7)まとめ
国民の喫煙対策に関する関心は高く、しかも近年さらに高まっているといえる。喫煙者を含めた国民にも喫煙対策は支持されるようになってきた。今後は、さらに具体的な対策を推進するための情報を提供できるように、世論調査を継続していくことが大きな社会的意義を持つようになる。
| 【参考文献】 |
|
総理府広報室:日本人の酒とタバコ.大蔵省印刷局、1989.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 441号.時事通信社、1987.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 510号.時事通信社、1989.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 546号.時事通信社、1990.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 588号.時事通信社、1991.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 626号.時事通信社、1992.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 668号.時事通信社、1993.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 699号.時事通信社、1994.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 767号.時事通信社、1996.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 785号.時事通信社、1997.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 831号.時事通信社、1998.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 870号.時事通信社、1999.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 910号.時事通信社、2000.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 952号.時事通信社、2001.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 1023号.時事通信社、2002.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 1062号.時事通信社、2003.
|
|
時事通信社:時事世論調査特報 1093号.時事通信社、2004.
|
|