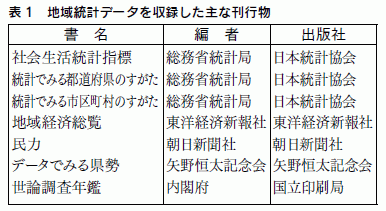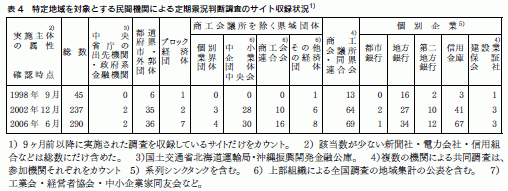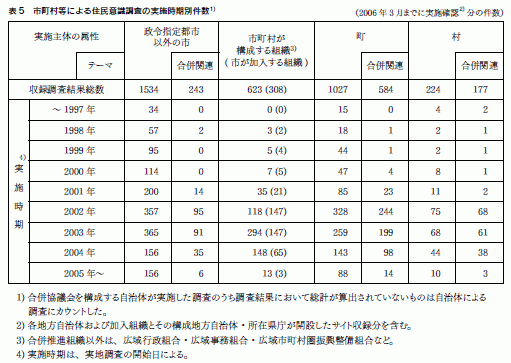|
■ インターネットを利用した地域統計データの入手法
国士舘大学政経学部 山田 茂
特定の地域に関する統計データが必要な機会が最近増えている。本稿では、地域住民を対象に実施された意識調査を含む地域統計データの作成状況とインターネットを利用した入手の方法を解説する。
まず地域別統計データを収録した刊行物からみていこう。表1に各分野全般を対象とする主な刊行物を掲げた。これらの発行周期はすべて1年である。刊行物は一覧性などの点において優れているが、必要なデータの網羅的な検索・入手タイミングと加工の容易さ・幅広い関連情報の入手などの点においてはインターネットを利用して提供されているデータの方が利点は多い。
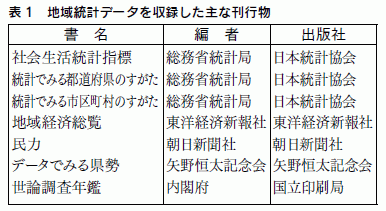
以下では急速に拡大しているインターネットを利用して提供されている地域統計データの概要とその入手方法を、データのタイプ別に紹介する。まず地域統計データのうちかなりの部分は、全国を対象とした統計データの一部として作成されている。これらの統計データは同一の規定に基づいて作成されているので、地域間の比較の際の制約はほとんどない。表2は、中央省庁などが作成する統計データとその関連情報を示したものである。
全国を対象として作成されている統計に含まれている地域別集計のうち月次・四半期などの短い周期のものの大半は、都道府県別までしか表章されていない。東北・中国などのブロック別までの表章のものも少なくない。ブロックの範囲は、ほとんどの場合出先機関などの担当地域と同一である。市区町村別まで表章されているものは、ごく少数の業務統計および比較的長い周期で作成されている全数調査とそれに基づく推計データだけである。これは、短い周期で作成されている大部分の統計が標本調査によって作成されているためである。
また、民間機関が作成する統計の中には全国集計だけが公表されていて地域別集計がまったく提供されていないものが多い。例えば、小売業界の団体による売上高統計のうち百貨店業界によるものには地域別集計が含まれているが、スーパー・コンビニエンスストア業界によるものにはない。個別企業による月次売上高の公表も最近拡大しているが、地域別集計はほとんど公表されていない。なお、民間機関の中にはサイト内の地域別集計の閲覧を関係者(業界団体の会員企業、その調査の回答企業など)に限っているものもある。
つぎに、中央省庁などの出先機関の一部・地方自治体などが管轄地域を対象にそれぞれ独自に作成・公表している統計をみてみよう(表3)。これらの統計はそれぞれ所在地域の事情に合わせて作成されているので、結果を他の統計と組み合わせて利用する際には、制約がある場合が多い。なお、これらの統計作成機関のサイトへは、本省・本店などのサイトに設けてあるリンク集を利用すれば容易にアクセスできる。
1)北海道は道内地区別の表章あり。
ここで各地域において独自に作成されているデータを、その作成方法の点からみてみると、業務統計、調査統計および加工統計に分かれる。まず地域別の業務統計は、中央省庁・地方自治体・民間企業などから多数公表されているが、その利用にはデータ作成の源泉である各機関の業務の実情を十分把握しておく必要がある。このうちエネルギー供給業・交通関係企業などが提供するデータは、その企業の地域内でのシェアが高い場合には利用価値が大きい。
他方、地域独自の調査統計のうち作成件数が最近増えた類型は、地域内の企業を対象とする景況判断調査と住民を対象とする意識調査である。
そこでこの2つの類型の統計の作成状況を立ち入ってみてみることにする。表4は、特定地域の企業を対象とする景況判断調査の結果を自身のサイトに収録している作成機関数の推移を示したものである(結果の閲覧に制限がないページに収録された調査に限定した)。大部分の区分において2002年前後までは急速に増加していたが、その後は概ね漸増傾向となっている。作成周期は4半期が大半である。景況判断調査の結果は、地域内での関心が高く、比較的頻繁に内容が更新されるので、再閲覧が期待できるコンテンツといえる。
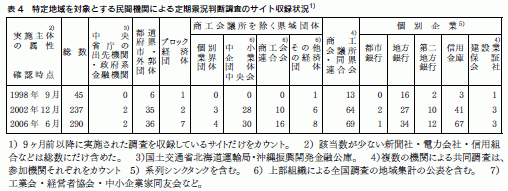
このうち新聞社と小規模な地域金融機関による調査は全体の傾向とは逆に最近減少傾向をみせている。前者については収録ページの有料閲覧部分への変更が、後者については作成機関自体の経営不振・統合による作成中止が減少の主な理由と考えられる。
これらの地域独自の調査が実施されるのは、対象企業の本社所在地を基準とする全国調査の地域別集計だけでは、地域経済の実情把握には不十分であると考えられたためであろう。この種の調査の対象企業をみると、地元企業だけに限定したものと本社が他地域に所在する企業を含めているものがある。一般に地域独自の調査の方が、小規模企業のウエイトが大きい。また、調査項目の内容と形式も独自性が強い。
これらの調査結果を収録したページへのアクセスには、中小企業庁とその外郭団体・政府系金融機関・中小企業団体などのサイトに設けられているリンク集を利用すると良い。
つぎに、特定地域を対象とする住民意識調査の状況をみてみよう。表5は市町村および市町村の連合体などによって実施された調査のうちインターネットに結果が収録されたものの件数を示したものである。ここでは一部が『世論調査年鑑』に掲載されている都道府県・政令指定都市によるものは省いた。
以前は実地調査の1年~2年後に発行される『世論調査年鑑』に掲載されている調査しか把握できなかったが、インターネット上への調査結果の公表の拡大により町村・合併協議会などによる調査のかなりの部分も実施後短期間のうちに利用できるようになった。一見してわかるように、市町村合併関連の住民意識調査の実施が2001年頃から増加している。これは、2006年3月末を期限とする合併優遇策の適用を目的とした合併推進の動きを反映したものである。このような合併関連の調査結果のうち合併協議が不調に終わった場合や実施主体であった市町村の合併による消滅などの場合には、サイト上から削除されてしまったものが多い。
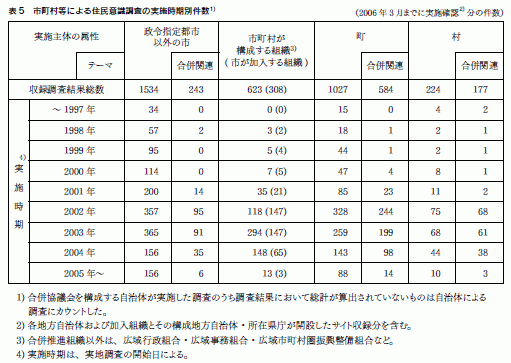
他方、合併関連以外の一般的なテーマに関する調査の中には相当長期間の結果がインターネットサイトに収録されているものがある。例えば、新潟市では1969年以降の実施分および同市と合併した市町村の実施分が、静岡県富士市では1970年以降の実施分がサイトに収録されている。
ところで、地域統計データから作成される加工統計の中では、景気動向指数(DI)が目立った存在となっている。地域DIは、東京周辺などを除く三十数県において道府県や民間機関によって現在継続的に作成されている。ほとんどの地域DIの作成方法は内閣府作成の全国DIと共通であるが、DIを構成する個別指標にはその地域の産業構成に即した地域データが加えられている。このように多数の景況判断調査や地域DIが各地域において独自に作成されていることには、各地域の経済動向が全国レベルのものとはかなり異なっていることが作用している。
最後に、各地域で独自に作成されている統計データを入手するための具体的な手順に触れておこう。入手したいデータを含む統計の正確な名称や作成機関の明細は、通常当初は不明なことが多い。このような場合、一般的な統計の名称をキーワードとして検索エンジンに入力する方法が思い浮かぶ。しかし、地域独自で作成されているデータの場合は同一分野の統計や意識調査に様々の名称(例 景況調査では「景気動向調査」「業況調査」「経営動向調査」など、意識調査では「アンケート」「意向調査」「世論調査」など)が使われているので、探しているデータに短時間でアクセスすることは難しい。
このような場合には、その地域の統計作成や意識調査の実施状況に通じている地方自治体の統計主管課・商工会議所・地域シンクタンク・中央省庁の出先機関などが設けているリンク集の利用を試みると良い。なお、都道府県の統計主管課のサイトには総務省統計局のサイト内のリンク集を経由して、市区町村の統計主管課のサイトには都道府県の統計主管課のサイト内のリンク集を経由して、アクセスできる。
他方、住民意識調査の結果の多くは、都道府県・市区町村の広報・広聴部門のページに収録されているが、中央省庁のサイトからの網羅的なリンク集は見当たらない。ただ一部の県の市町村合併推進部局のサイトには県下の市町村による意識調査結果の概要を収録したものがある。
また、地方銀行や電力会社の系列シンクタンクを中心とする民間調査機関や商工会議所も、データの具体的な分析を数多く手掛けているだけに、その地域独自の重要データの解説やデータ作成機関のページへのリンク集などの有益な情報をサイト内で提供している。
以上みてきたように多数の地域統計データがインターネット上で継続的に提供されており、多少の工夫をすれば、各種のデータを比較的短時間で入手することができる。
なお、本稿において紹介したインターネットサイトのURLは、筆者の個人サイト(http://home.t06.itscom.net/ecyamada/)内に『統計資料集 2006』の掲載内容の一部として収録しているので、ご利用いただければ幸いである(本稿に掲載した各サイトのURLは2006年6月に確認)。
|