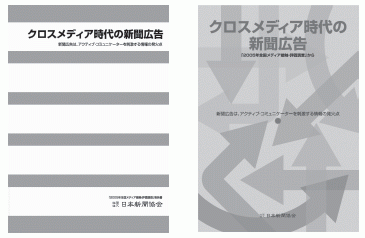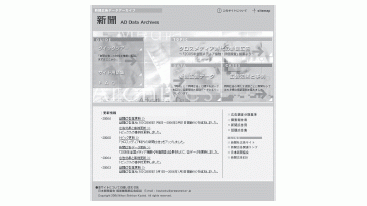|
社団法人 日本新聞協会
1.新聞は日常生活に欠かせないマスメディア 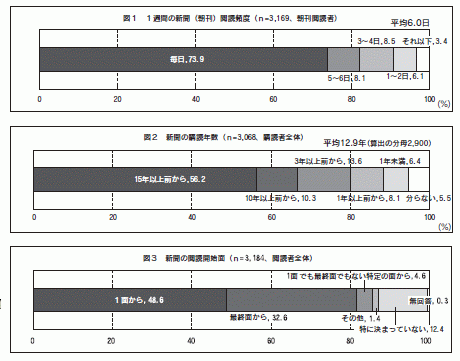
表1は、各メディアとの接触が1年前に比べて「増えた」と思うか「減った」と思うかを聞いた結果です。全体で「増加」が「減少」より多かったのが、「新聞を読む時間」「インターネットを使う時間」などですが「、減少」の方が多かったのが「テレビでNHK(地上波)を見る時間」「テレビで民放(地上波)を見る時間「」雑誌を読む時間」「書籍・単行本を読む時間」などでした。このことから、メディアからの情報量がはんらんする今も、メディアの中心たる新聞の価値が、改めて重用されていることが推察できます。 
表2は、各メディアの広告がどのようなイメージで見られているのかを聞いたものです。新聞広告は「情報が信頼できる」「内容が公平・正確」など、理性的な項目でトップにあげられています。また、「役に立つ広告が多い」「必要な情報を改めて確認する」など、実用性の面でも高い評価を得ています。さらに、新聞広告は「企業の姿勢や考え方が伝わってくる」の項目では他メディアに比べ評価が最も高く、企業のブランド構築に寄与できる広告メディアであることを再確認できました。 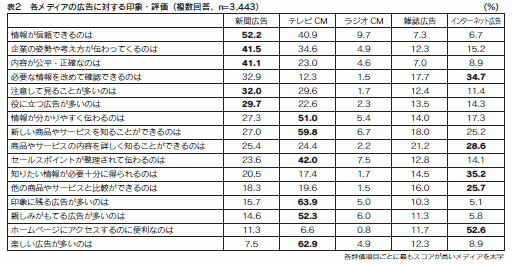 2.クロスメディア時代の新聞広告 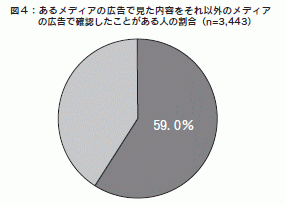
広告情報の確認経路を、新聞広告を中心に見たものが図5です。新聞広告と他のメディアを使って広告情報を確認する人のうち、「テレビCMで見た内容を新聞広告で確認する人」は45.1%、逆に「新聞広告で見た内容をテレビCMで確認する人」は35.8%で、新聞広告とテレビCMは互いに補完的な情報確認が行われており、緊密な関係にあるといえます。また、「新聞広告で見た内容をインターネット広告で確認する人」は43.6%に達しました。逆の流れが7.8%にとどまることから、新聞広告を起点にしてインターネット広告で確認するという流れがあることが分かりました。 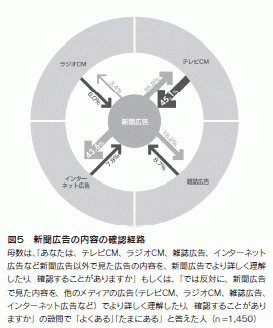 (2)アクティブ・コミュニケーターと新聞 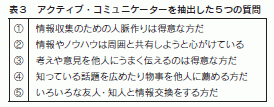
複数メディア間で広告情報を確認している人の割合が約6割と前述しましたが、この割合はアクティブ・コミュニケーターの度合いに応じて高くなり(図6)、彼らは複数のメディアをクロスして活用していることが分かります。このうち、新聞広告の情報をインターネットで確認する人の割合を見ると(図7)、全体の43.6%に対して、
アクティブ・コミュニケーター 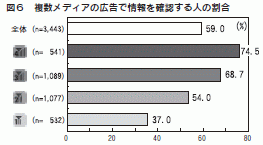 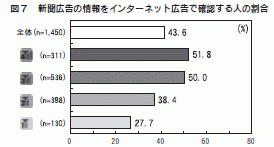
アクティブ・コミュニケーターには、年齢が若く、高収入、高学歴の傾向があります(表4)。さらに、商品・サービスへの関心を見てみると(図8)、ほぼすべての項目でスコアが高くなっています。アクティブ・コミュニケーターはマーケティング・ターゲットとして非常に魅力的です。 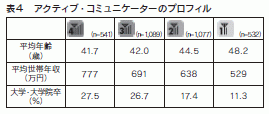 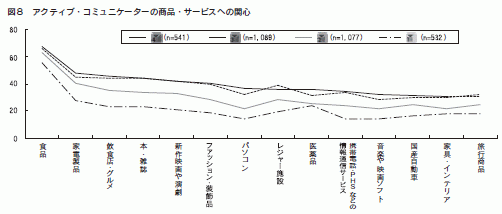
図9は、アクティブ・コミュニケーターによる各メディアの接触量を「時間×頻度」で測定し、平均値を境に「高接触者」と「低接触者」に分類して、高接触者の割合を調べたものです。新聞とインターネットは、アクティブ・コミュニケーターであるほど高接触者の割合が高まります。一方、テレビにはその逆の傾向が見られます。次に、各メディアの接触者の割合を見ると(図10)、インターネットがよりアクティブ・コミュニケーターに接触されるのに対し、新聞とテレビはどの層もほとんど変わりません。つまり新聞は、誰からも毎日のように読まれるマスメディアであるとともに、アクティブ・コミュニケーターにより深く読まれる性質を持つメディアであるといえます。 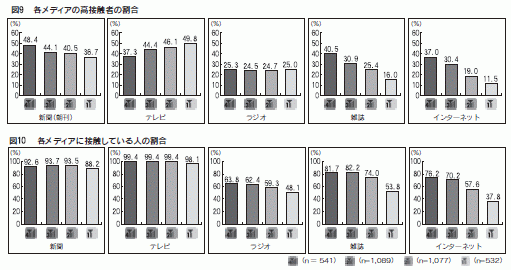
先ほど、表1で個々のマスメディアに接する時間が1年前と比べて「減った」と感じている人が多いというデータを紹介しましたが、メディアの多様化、細分化が進み、人々のコミュニケーション経路が複雑さを増すなかで、特定のメディアだけで情報を伝えることが難しくなってきています。そのような時代だからこそ、メディア間の情報確認経路を考慮したクロスメディアのコミュニケーションデザインが求められています。
|
 は51.8%と、新聞広告を起点にインターネット広告で情報を確認する割合が高まっています。
は51.8%と、新聞広告を起点にインターネット広告で情報を確認する割合が高まっています。