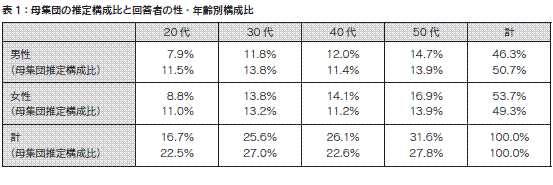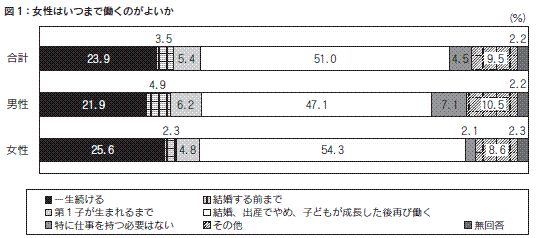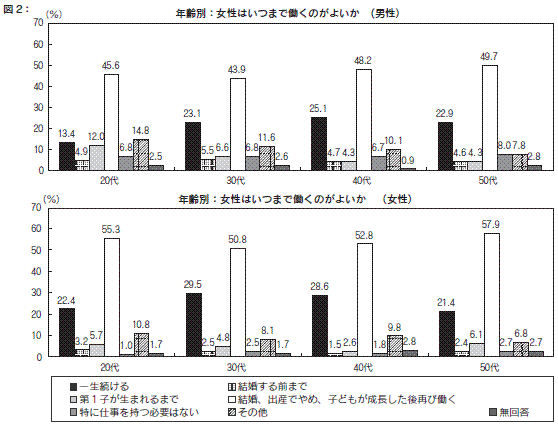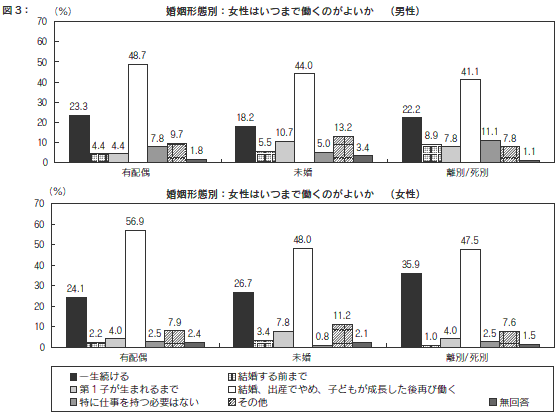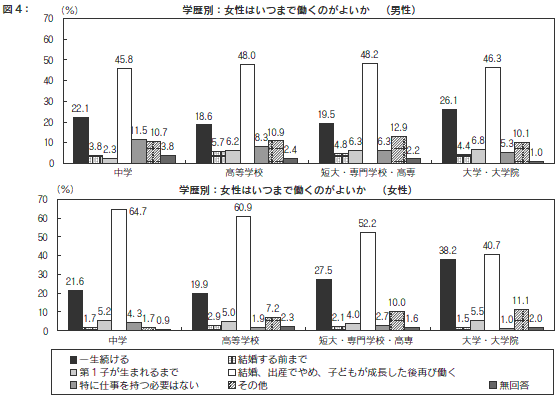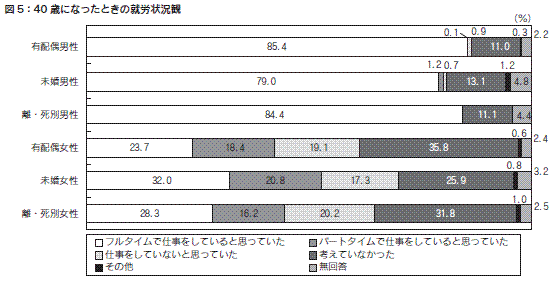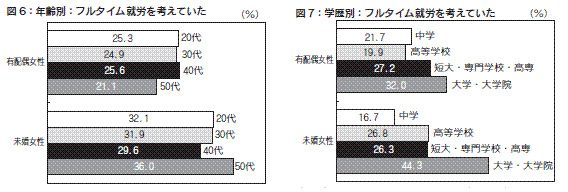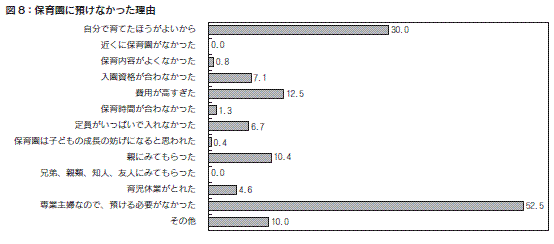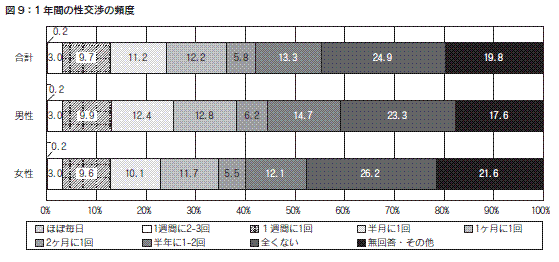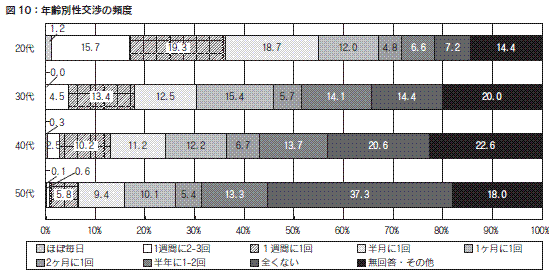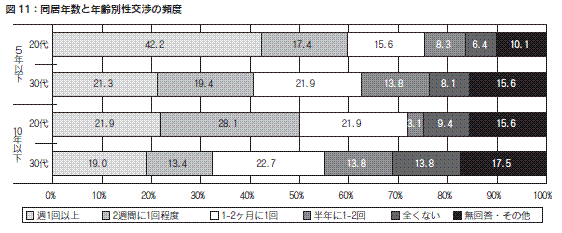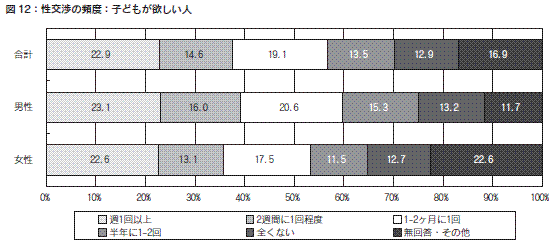■ 全国調査「仕事と家族」より
女性の就労観と夫婦間の性交渉の頻度について
日本大学人口研究所 森木 美恵
1.はじめに
日本大学人口研究所は世界保健機関(WHO)と共同で「仕事と家族」に関する全国調査を実施した。
当研究所は、2007年にWHOより人口・保
健・開発の3分野でのコラボレーティング・センターとして認定され、
その役割の一つとして先進国における低出生とリプロダクティブ・ヘルス(性と生殖に関する健康)の問題について研究を進めている。
日本は世界で最も低出生が進行している国の一つであるとともに、
近年には低出生国ならではの新しいリプロダクティブ・ヘルスに関わる問題も論じられている。
リプロダクティブ・ヘルスについては、発展途上国における開発と出生力低下を目指す枠組みの中で論じられることが多く、
先進国においては、リプロダクティブ・ヘルスの問題と出
生力を結び付けて取り上げられることは今まであまりなかった。
しかし、現実には配偶者間の性交渉の頻度や不妊といった低出生に関係した新たなリプロダクティブ・ヘルスに関する問題が浮上しており、
その実態についての調査研究の必要性が認識され始めている。
今回の全国調査の主な目的は、低出生とリプロダクティブ・ヘルスに関する事柄に焦点を当てて学術的なデータを収集することであった。
収集したデータの分析結果は、日本大学人口研究所がWHOおよび国際人口学会(IUSSP)と共同で2008年11月に東京で開催する国際会議
「アジアにおける低出生とリプロダクティブ・ヘルス」において発表する予定である。
この国際会議では、「低
出生のメカニズム」と「低出生国におけるリプロダクティブ・ヘルス」の2点を軸に、
日本を含めたアジアの多くの国々が抱える低出生国における人口問題についての研究成果を報告する。
特に、低出生国におけるリプロダクティブ・ヘルスについては、人口学の分野でも比較的新しい視点であるため、問題の現状があまり明らかになっていない。
この国際会議は、アジアにおける低出生国全体を視野に入れて、研究成果をまとめるという意味で有意義な試みになると期待される。
本稿では、全国調査「仕事と家族」の調査結果から、「仕事」と「家族」の両側面より1点ずつ低出生とリプロダクティブ・ヘルスに関する問題を提示する。
2.調査の方法
調査は全国の満20歳以上59歳以下の男女計9000人を対象に、2007年4月7日から 4月30日に留め置き法(調査員が該当者を訪問して記入を依頼、のちに調査票を回収)で行った。
また、調査の際に不在のためにコンタクト出来なかった人や第1次拒否者を対象に、5月25日から7月18日の期間に留め置き郵送法(調査員が調査票を訪問配布し、のちに回答を郵送で回収)や
郵送法(郵便にて調査票を配布、回収)を用いてフォローアップ調査も行った(本調査、フォローアップ調査ともに 4月10日時点の状況を回答)。
なお、実査および調査票の点検・管理は社団法人中央調査社に委託した。
抽出方法については、基本的に住民基本台帳を使用して層化2段無作為抽出法で行った。
層化の方法として、全国を9ブロック(北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州)、
さらに各ブロックを都市規模別(大都市、人口20万人以上の市、人口10万人以上の市、人口5万人以上の市、人口5万人未満の市、その他の市町村)に6分類した。
平成12年国勢調査時に設定された調査区の基本単位区を第1次抽出単位として上記計53地区層(四国ブロックには大都市の該当なし)の中から500地点を無作為に抽出した。
さらに、第2次抽出段階として、抽出された500地点にある世帯の中から、層別推定母集団の規模に従って比例配分で計9000名を無作為に抽出した(抽出台帳として住民基本台帳を使用)。
なお、住民基本台帳の閲覧が自治体により許可されなかった場合(計500地点中16地点)は、住宅地図データベースを使用して層化3段無作為抽出法によって対象者の抽出を行った。
アタック総数9000件のうち最終有効回収数は4624件で、回収率は51.4%(4624/9000)であった。
欠票調査票数(4376件)のうち、欠票理由の内訳は転居(370件、欠票数の8.5%)、住所不明(51件、欠票数の1.2%)、長期不在(58件、欠票数の1.3%)、
一時不在(59件、欠票数の1.3%)、その他(164 件、欠票数の3.7%)、拒否(3674 件、欠票
数の84.0%)だった。
欠票理由のうち対象不適格とみなすことが出来る「転居」、「住所不明」「死亡を含むその他」をアタック総数から除くと、回収率は若干上がり、
54.9%[4624 / {9000-(370+51+164)}]になる。
表1は母集団の推定構成比と回答者の構成比を性・年齢別に比較したものである。
母集団の推定構成比に比べて、20歳代の回答者の比率が男女ともに低い傾向が見られ、反対に50歳代の回答者の比率が若干高くなっている。
性別では、女性の方が多少高い比率で含まれている。回答者の構成比と母集団の推定構成比の差を補うために、
推計人口数と回答者数の割合より比推定して回答者数の少なかった層に対して重み付けをすることも考えられるが、
補正により混乱を招くこともあり得るので、以下の報告では重み付けはされていない。
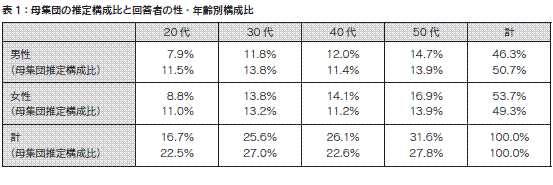
3.「仕事」について-女性と就労観:「働き続ける」は小数派-
少子高齢社会における労働力不足を緩和する政策の一つとして、女性の継続した就労を目指す様々な仕事と家庭の両立策が進められている。
しかし、「女性が働き続ける」という価値観・選択肢には依然として重きが置かれていない現状が「仕事と家族」調査結果より示された。
まず、「一般的に言って女性はいつまで仕事を続けるのがよいと思いますか」という質問に対して、男女合わせて過半数の51.0%(男性47.1%、女性54.3%)が
「結婚、出産で仕事をやめ、子どもが成長した後再び働く」といういわゆる「M字型」の働き方が女性の働き
としてはよいとした(1)。
一方、「一生続ける」のがよいと思うと回答したのは男性の21.9%、女性の25.6%のみであった(図1)。
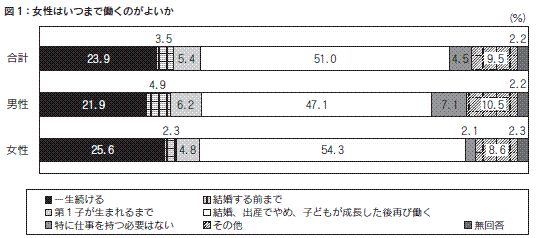
結婚、出産、育児でいったん離職する働き方をよいとする考え方は年齢、婚姻形態、学歴に関わらず幅広く見られた。
年齢別では、「結婚、出産で仕事をやめ、子どもが成長した後再び働く」のがよいとした割合は、どの年齢層でも男性は40%以上、女性は50%以上を占めた。
また、「一生働く」のがよいと考えている割合は、20歳代でむしろ低い傾向にあり、特に男性の間でその傾向が目立ったのが特徴的であった(図2)。
婚姻
形態別でも、既婚者未婚者ともに男女の別なく40%以上が「結婚、出産で仕事をやめ、子どもが成長した後再び働く」のがよいとした。
しかし、「一生働く」のがよいと考えている割合は、女性の離・死別者では35.9%と比較的高かった(図3)。
学歴別では、男性はどの学歴においても「結婚、出産で仕事をやめ、子どもが成長した後再び働く」が45%以上を占めた。
一方女性は、大学・大学
院卒が40.7%と、他の学歴の女性と比べて低く、結婚・出産にかかわらず継続して就労しようという割合が高くなっている(図4)
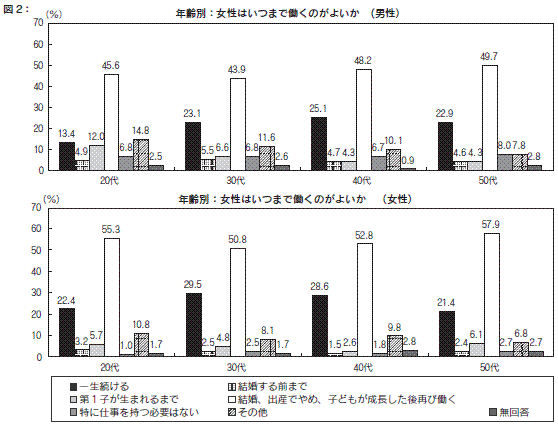
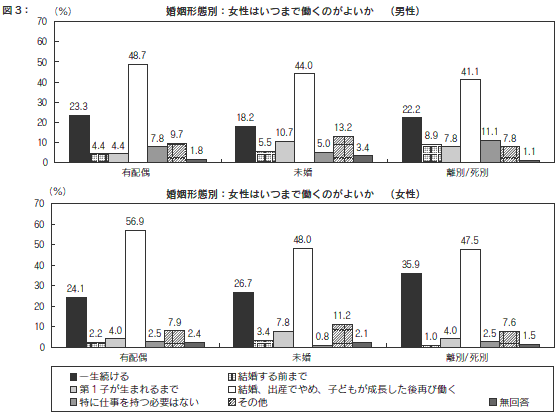
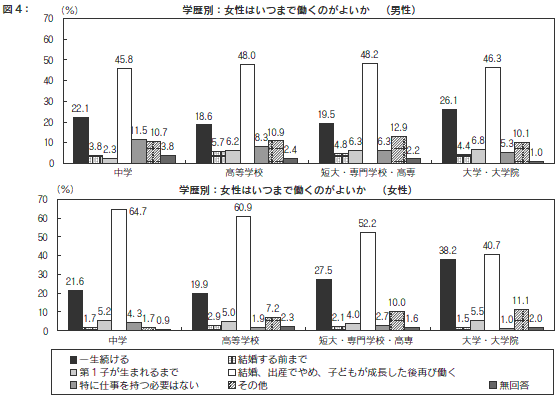
女性が「働き続ける」という考え方がいまだ少
数派であることの背景には、仕事と家庭の両立が難しい現実を感じ、その結果、
継続したキャリア形成を目指すよりも、子育て期にあってはいったん離職するという現実的な選択がされているとも考えられる。
しかし一方では、以下の質問に対する回答から見られるように、まだ社会に出る以前の最終学校を卒業した時点で既に
「フルタイムで働き続ける」という就労観を持った女性が少ない
様子がうかがえた。
調査結果によると、「最終学校を卒業した時に、自分が40歳になるころ仕事をしていると思っていたかどうか」という質問に対して、
有配偶女性の23.7%、離・死別女性の28.3%と未
婚女性の32.0%のみが「フルタイムでの仕事」を
考えていたと回答した(2)。
女性の場合は、「パートタイムで仕事をしていると思っていた」、「仕事をしていないと思っていた」、「考えてなかった」という回答の割合の多さが示すように、
継続就労してキャリアを築きたいという割合は学校を卒業した時点で既に低かったと考えられる。
男性に関しては、大多数がフルタイム雇用を考えていた(図5)。
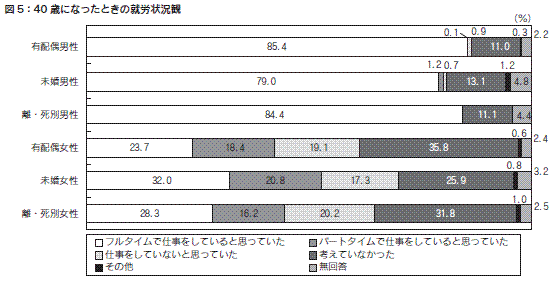
また、「40歳になった時にフルタイムで仕事を
している」と考えていた女性の割合は、年齢層に関係なく低く、20歳代から50歳代を通じて、
有配偶者は約4分の1、未婚者では約3分の1だった(図6)。
学歴別では、大学・大学院卒の未婚女性にフルタイム雇用を考えていた割合が目立って高かった(44.3%)が、同学歴の有配偶女性は、
他の学歴の有配偶者よりは高いものの、それでも約3割程度(32.0%)であった(図7)。
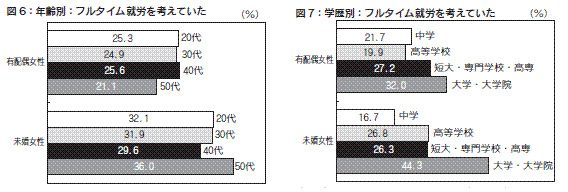
仕事と家庭の両立を可能にし、女性の継続した就
労を促進する政策の一つとして、政府は保育園の待機児童数を減らす試みに取り組んでいる。
しかし、以前にも指摘されているように(小川2005)、保育園に子どもを預けなかった主な理由は「働き続けること」よりも「家庭での保育」、
つまり「母親業」を重視した結果だということが今回の調査結果でも示された(3)。
現在0歳から3歳未満児がいる回答者で、その子どもを保育園に預けている割合は22.6%であった。
全体の約80%にあたる、
預けていない人のうち、(一番下の子を)預けていない主な理由は、「自分で育てたほうがよいから」、
「専業主婦なので預ける必要がなかった」だった(4)。
一方、「近くに保育園がなかった」、「定員がいっぱ
いで入れなかった」など保育施設の不足から利用をしなかった(できなかった)とした割合は少数だった(図8)。
今後、女性の継続した就労を期待するためには、局地的に保育施設が不足している現状の改善と共に、
全体としては子育て観を含めた包括的な就労観の変化が必要となってくるのではないか。
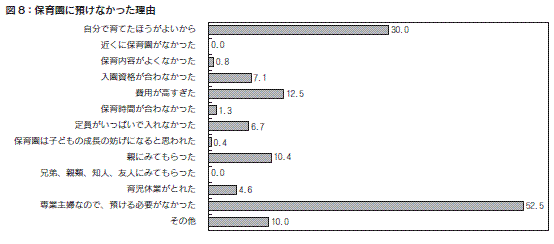
4.「家族」について-夫婦間の性交渉の頻度:その実態は?-
低出生国におけるリプロダクティブ・ヘルスに関する問題の一つとして夫婦間の性交渉の頻度が挙げられる。
しかし、日本におけるいわゆる「セックスレス」カップルの存在については、雑誌やインターネット調査などを通じて今までにも一般に取り上げられることはあったものの、
全国規模で学術的に収集されたデータは少なく、実態が明らかになっていない。
数少ないデータのうち、日本版General Social Surveys(大阪商業大学比較地
域研究所、東京大学社会科学研究所)の2000年と2001年では過去1年間のセックスの頻度を聞いているが、
プライベートな質問であるからか、回答のうち「回答したくない」「無回答」が約40%を占めている(5)。
そのため、2004年と2006年に行われた第2、3 回「男女の生活と意識に関する調査」(日本家族計画協会)が性交渉の頻度について知る実質的なおそらく唯一のデータソースであった。
今回、全国調査「仕事と家族」では性交渉の頻度を日本におけるリプロダクティブ・ヘルスの問題の一つとして捉え、その実態を調査した。
特に、夫婦間の性交渉の頻度は、低出生の要因を考える上で基本的ながらも重要な側面を持つという観点から、
「夫婦間」に限定して過去1年間の性交渉の頻度を聞いた(6)。
人口学における生物学的アプローチで有名なボンガーツとポッター(1983)によると、人口における妊孕力は性交渉の頻度に直接関係しているという(7)。
例えば、彼らの推計では週平均 0.27回(月約1回)の性交渉があったとして妊娠するまでに約 42.8ヶ月、週平均 1.08回で 11.5ヶ月、週平均 2.15回で 6.3ヶ月かかることになる。
もちろん、実際には個人個人の様々な生物学的要件が関わってくるので一概には言えないが、
低出生の一因として性交渉の頻度という生殖の基本的行為を見過ごしてはならないことを示唆している。
「仕事と家族」調査結果によると、ここ1年間に性交渉が「全くない」夫婦が、全体の約4分の1(24.9%)を占めた(「その他」1.5%を含む 19.8%が「無回答」)。
性別では夫婦間の性交渉の頻度に明らかな差は見られなかった。頻度の詳しい内訳は図9の通りだが、
日本性科学会は、セックスレスを「特殊な事情が認められないにもかかわらず、カップルの合意した性交あるいはセクシュアル・コンタクトが1ヶ月以上なく、
その後も長期にわたることが予想される場合」と定義している。
本調査結果をこの定義にあてはめると、20歳から59歳の夫婦の 44.0%(2ヶ月に1回 5.8%、半年に1-2回 13.3%、全くない 24.9%の計)がセックスレスであるという結果になる。
ちなみに、2006年に行われた第3回「男女の生活と意識に関する調査」調査結果によると、
婚姻関係にある回答者(対象は16歳から49歳の男女)の 34.6%がセックスレス(この1ヶ月で性交渉の回数がなかった割合)であった(7.0%が無回答)(8) 。
今回のデータを20歳から49歳に限定して計算すると 36.3%(2ヶ月に1回 6.1%、半年に1-2回 13.3%、全くない 16.9%の計)がセックスレスということになり、
2006年の結果と近似した値になる。
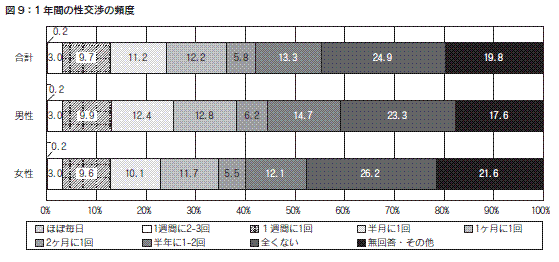
年齢別で性交渉の頻度を見ると、ここ1年間で全く性交渉がなかった割合は、20歳代では 7.2%と比較的少ないが、30歳代で 14.4%、40歳代で 20.6%、50歳代で 37.3%と、
年齢と共にその割合が上昇した(図10)。
しかし、全くのセックス「レス」ではなくても、比較的若い年齢層で、かつ一緒に住み始めてからの期間が短い人でも、性交渉頻度がさほど多くないことが目立った。
同居年数5年以下の20歳代で「週1回以上」性交渉があったと答えた割合は半分以下(42.2%)で、「2週間に1回程度」が 17.4%、「1-2ヶ月に1回程度」が 15.6%、
「半年に1-2回程度」が 8.3%だった。
同居年数5年以下の30歳代では、定期的に性交渉を持つ夫婦の割合はさらに低くなり、「週1回以上」性交渉があった夫婦は 21.3%に過ぎず、「2週間に1回程度」が 19.4%、
「1-2ヶ月に1回程度」が 21.9%、「半年に1-2回程度」が 13.8%だった(図11)。
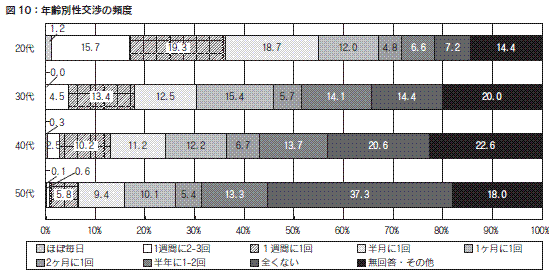
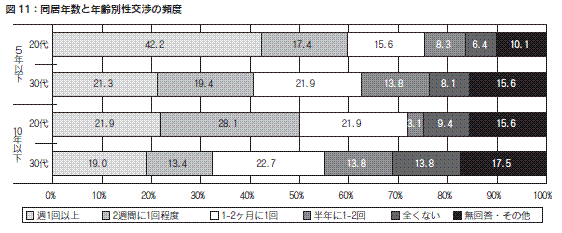
さらに、低出生との関係では、結婚していて「子どもを欲しい」と思っている人の中でも、「週1回以上」の性交渉があった割合は約4分の1以下(22.9%)で
「2週間に1回程度」が 14.6%、「1-2ヶ月に1回程度」が 19.1%、「半年に1-2回程度」が 13.5%、そして「全くない」が 12.9%であった(図12)。
性交渉の頻度と出生率の関係についての詳しい分析は冒頭で述べた11月の国際会議で発表される予定であるが、
今回の調査より夫婦間の性交渉の頻度を低出生国日本における重要なリプロダクティブ・ヘルスの問題として位置づける必要性が示された。
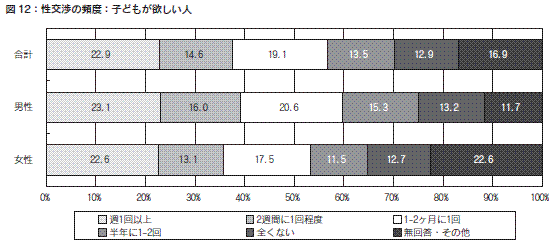
5.終わりに
本稿では全国調査「仕事と家族」の背景、調査概要、調査結果の一部を簡単に紹介した。
世界でも最も低出生が進んでいる国の一つである日本における、「仕事」と「家族」の両領域での今後の課題について考える一助になれば幸いである。
今回の調査では、調査目的の関係上、プライベートかつ詳細なデータを収集したが、他の調査と比較しても信頼し得るデータが集まったと考えている。
それも調査にご協力くださった地方自治体の方々を始め、実際に調査票を記入してくださった調査対象の皆様のお陰である。
また、調査にご尽力くださった中央調査社にもこの場をかりてお礼を申し上げたい。
今回の調査をもとに、第2回全国調査「仕事と家族」を2009年4月に実施予定である。昨今ますます厳しくなっている調査票回収率の向上を目指して、
皆様のより一層のご理解とご協力をお願いする次第である。
(1) 回答者全員に対して、「あなたは、一般的に、女性がいつまで仕事を続けるのがよいと思いますか」と質問。
回答選択肢は「一生続ける」、「結婚する前まで」、「第1子が生まれるまで」、「結婚、出産でやめ、子どもが成長した後再び働く」、「特に仕事を持つ必要はない」、
「その他」。
(2) 現在結婚している人全員と未婚・離別・死別者全員に対して、「あなたは、最終学校を卒業された時に、ご自分が40歳になる頃、仕事をしていると思っていましたか。
在学中の方は、現時点でのお考えをお答えください」と質問。
回答選択肢は「フルタイムで仕事をしていると思っていた」、「パートタイムで仕事をしていると思っていた」、「仕事をしていないと思っていた」、「考えていなかった」、
「その他」。
(3) 小川直宏、2005、「女性の就業と子育て支援策に関する分析―育児休業取得と保育サービス利用の視点から―」、『超少子化時代の家族意識 第1回人口・家族・世代世論調査報告書』、
毎日新聞社。
(4) 現在結婚していて、子どもを保育園に預けたことのない人に対して、「保育園に預けなかった一番下のお子さんについてお尋ねします。
保育園に預けなかった理由は次のうちどれですか。あてはまる番号3つまで丸をつけてください」と質問。
回答選択肢は「自分で育てたほうがよいから」、「近くに保育園がなかった」、「保育内容がよくなかった」、「入園資格が合わなかった」、「費用が高すぎた」、「保育時間が合わなかった」、
「定員がいっぱいで入れなかった」、「保育園は子どもの成長の妨げになると思われた」、「親にみてもらった」、「兄弟や親類にみてもらった」、「知人や友人にみてもらった」、
「育児休業が取れた」、「専業主婦なので、預ける必要がなかった」、「その他」。
(5) 大阪商業大学比較地域研究所・東京大学社会科学研究所、2000&2001、『日本版 General Social Surveys JGSS-2000』 &『 日本
版 General Social Surveys JGSS-2001』、
東京大学社会科学研究所。
日本版General Social Surveys (JGSS) は、大阪商業大学比較地域研究所が、文部科学省から学術フロンティア推進拠点としての指定を受けて(1999-2003 年度)、
東京大学社会科学研究所と共同で実施している研究プロジェクトである(研究代表:谷岡一朗・仁田道夫、代表幹事:佐藤博樹・岩井紀子、事務局長:大澤美苗)。
東京大学社会科学研究所付属日本社会研究情報センターSSJ データアーカイブがデータの作成に協力している。
(6) 現在結婚している人全員に対して、「あなた方ご夫婦のここ1 年間の性交渉の頻度は次のうちどれにあたりますか」と質問。
回答選択肢は「ほぼ毎日」、「1週間に2-3回」、「1週間に1回くらい」、「半月に1回くらい」、「1ヶ月に1回くらい」、「2ヶ月に1回くらい」、
「半年に1-2回くらい」、「全くない」、「その他」。
(7) Bongaarts, John, & Potter, Robert. (1983). Fertility, Biology, and Behavior: An Analysis of the Proximate Determinants. NewYork: Academic Press.
(8) 社団法人 日本家族計画協会、2007、『第3回 男女の生活と意識に関する調査報告書』(平成19年度厚生労働科学研究費補
助金研究 望まない妊娠、
人工妊娠中絶を防止するための効果的な避妊教育プログラムの開発に関する研究)、社団法人 日本家族計画協会。
|