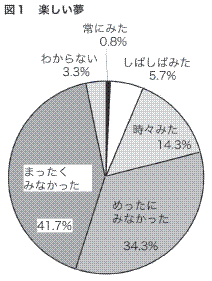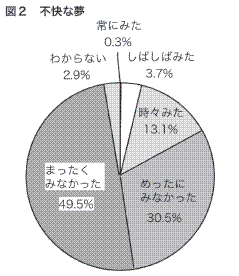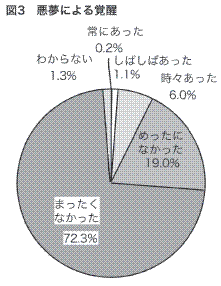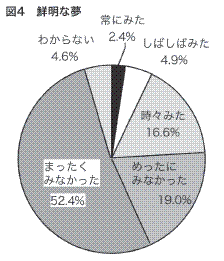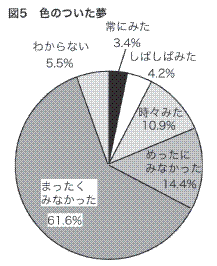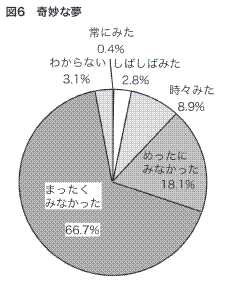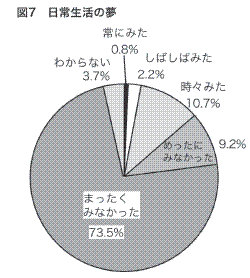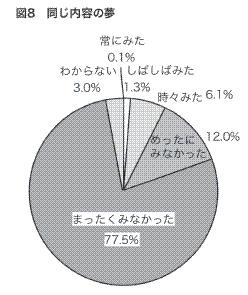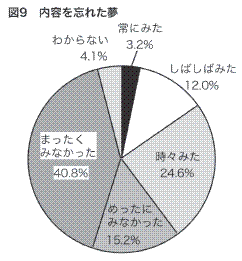■ 夢の頻度に関する調査研究
警視庁科学捜査研究所 鈴木 博之
日本大学医学部 公衆衛生学部門 兼板 佳孝
日本大学医学部 公衆衛生学部門 大井田 隆
はじめに
夢をみたことのない人はいないであろう。しかし、昨日夢をみましたか?と聞かれたとき、すべての人がみたと答えるわけではない。
毎日夢をはっきり覚えていて、それを日記につけているという人がいれば、「そういえば最近夢をみていない」というように夢をみたという認識がない人も多いであろう。
また、「最近以前よりも夢をよくみる」、というように、夢見の頻度に変化を感じることもある。
夢見の頻度は人それぞれ異なり、何らかの理由で変化していると思われる。
大学生など少数のサンプルを対象にした夢見に関する調査はこれまでにも行われてきており、理科系、文科系の大学生の約50%が色つきの夢をみていることが報告されている
(1)。
一般人口を対象にした夢見に関する研究は、悪夢と精神的健康の関係を調べる目的では行われているが(2)、
楽しい夢、不快な夢、色つきの夢といった夢見の頻度を調べた疫学研究はこれまでにほとんど行われていない。
本調査は日本における一般人口の夢見の頻度を全国調査により明らかにすることを目的とした。
対象と方法
本調査は2008年2月に実施した。本調査は全国20歳以上の男女4,000人を対象に、面接聴取法で実施した。
過去一ヶ月間に体験した様々な種類の夢見に関する質問を行い、一般人口における夢見の頻度を検討した。
夢に関する質問は、楽しい夢、不快な夢、悪夢による覚醒、鮮明な夢、色のついた夢、奇妙な夢、日常生活の夢、同じ内容の夢、内容を忘れてしまった夢について質問し、
「常にみた」「しばしばみた」「時々みた」「めったにみなかった」「まったくみなかった」「わからない」のいずれかで回答を求めた。
結果と考察
有効回収数は1,308であり、男性 589名、女性 719名から回答が得られた。
みた夢を評価し、その種類を分類するときにまず思いつくのはいい夢か嫌な夢かであろう。
はじめに「楽しい夢」「不快な夢」の頻度を求めた。
(1)楽しい夢
誰もが楽しい夢をみたいと思っているだろうが、実際にその願いをかなえている人はどのくらいいるのだろうか。
常に楽しい夢をみたと答えたのは回答者の約1%であり、しばしばみた、時々みたをあわせると、約2割の人が楽しい夢をみたと感じていることがわかった。
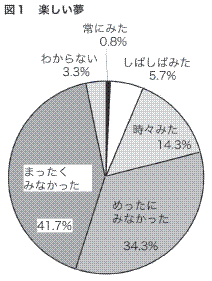
(2)楽しい夢
反対に不快な夢はどうであろうか。常にみたという回答は、0.3%と非常に低く、しばしばみた、時々みた、の合計は 17.0%であった。
楽しい夢に比べると少し低い割合であることが分かる。
まったくみなかったという回答が約半分を占めることも不快な夢の頻度が楽しい夢と比べて低いことを表しているようにみえる。
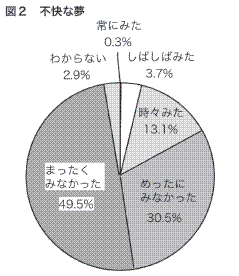
(3)悪夢による覚醒
不快な夢の中でもその程度が強いものは悪夢として認識される。睡眠障害国際分類(3)では悪夢の定義に睡眠からの覚醒を含めているため、
今回の調査では「あなたは、この1ヶ月間、恐ろしい夢で目が覚めることはありましたか」という質問を用いた。
常にあったが 0.2%、しばしばあったが 1.1%、ときどきあったが 6.0%であり、これらの合計は 7.4%と楽しい夢、不快な夢と比べて極めて低いことが分かる。
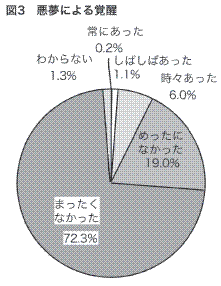
(4)鮮明な夢
はっきりと夢でみたものを覚えていることもあれば、ぼんやりとした印象しかないときもある。
「はっきりと映像がみえた鮮明な夢をみましたか」という質問を行った。
常にみた 2.4%、しばしばみた 4.9%、時々みた 16.6%、これらの合計が 23.9%であった。
この数値は楽しい夢、不快な夢よりも高く、特に常にみたと答えた割合は楽しい夢の3倍以上であった。
楽しい、不快というよりも、「はっきりと夢をみた」という認識のほうが高い頻度で現れると考えられる。
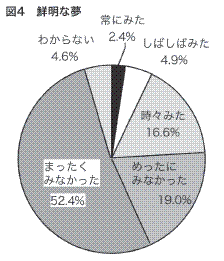
(5)色のついた夢
3.4%が常に、4.2%がしばしば、10.9%が時々、色のついた夢をみたと報告している。
これらの合計は 18.5%であり、楽しい、鮮明といった他の夢の分類と同様に約2割のものが色つきの夢を体験していることが分かる。
色のついた夢は色彩感覚に敏感な人だけがみると考えられがちであるが、そう珍しいものではないことがうかがわれる。
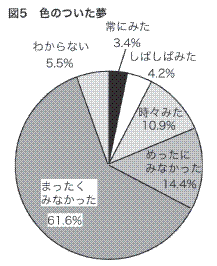
(6)奇妙な夢
夢が占いの題材や芸術作品のアイデアにもちいられたりする理由のひとつはその内容が奇妙であることであろう。
夢の内容が奇妙であり、コントロールできないことから古代の人は夢を神や悪魔からのメッセージであると考えてきた。
現代の一般人はどの程度奇妙な夢をみているのであろうか。
「非現実的な奇妙な内容の夢をみましたか」という質問に対し、常にみた 0.4%、しばしばみた 2.8%、時々みた 8.9%、これらの合計 12.1%という結果であった。
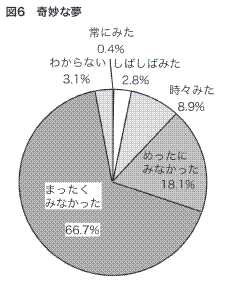
(7)日常生活の夢
奇妙な内容とは反対に、いつもの生活についての夢をみることはどのくらいあるのだろうか。
「日常で実際に体験した出来事を夢にみましたか」という質問に対して、常にみた 0.8%、しばしばみた 2.2%、時々みた 10.7%であり、合計は13.7%だった。
日常生活の夢は、奇妙な夢より少し高い頻度であったが、両方とも悪夢よりは高く、楽しい・不快な夢よりは低いというものであった。
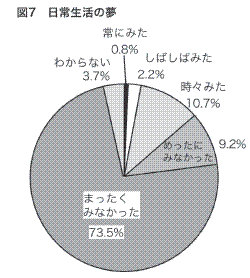
(8)同じ内容の夢
「この夢は前にみたことがある」と夢をみている最中や、目覚めたときに感じることがある。
同じ夢をみる頻度はどのくらいなのであろうか。
「同じ内容の夢をみましたか」という問いに対して、常にみたは 0.1%と極めて低く、しばしば、時々を合わせた合計は 7.5%であった。
この頻度は悪夢による覚醒と同程度であり、同じ内容の夢をみるというのは比較的まれな体験であると思われる。
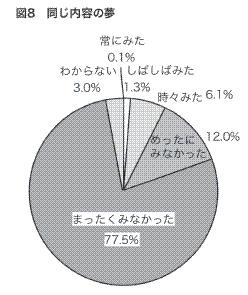
(9)内容を忘れた夢
目覚めたときに、何か夢をみていた気がするのだがどんな夢だったかは思い出せないこともよくある。
夢をみている時は記憶と関連する海馬が、新しい記憶を記名するのには適していない状態であるため、夢はすぐに忘れてしまい、思い出せないことが多いと考えられている。
また、実際にみた夢の内容をうまく言葉で説明できないこともありうる。
このような体験の頻度をとらえるために、「内容を忘れてしまったり内容を説明できないものの、何か夢をみたということはありましたか」という質問を行った。
常にみた 3.2%、しばしばみた 12.0%、時々みた24.6%、これらの合計が 39.8%だった。
この結果はそのほかの夢に関する質問よりも飛び抜けて高い値であり、多くの人が夢をみたときにその内容を意識することなく、なんとなく夢をみた気がする、
というように感じていることを示している。
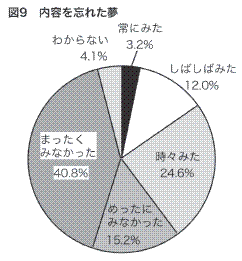
(10)何らかの夢をみた人の割合
1から9までの夢に関する質問のいずれか1つ以上に「常にみた」「しばしばみた」「時々みた」と答えた人を夢見体験ありと定義し、その頻度を算出した。
その結果夢見体験ありは 53.6%、夢見体験なしは 46.4%であり、約半数の人が過去1ヶ月の間に、何らかの夢をみたと認識していることが明らかになった。
おわりに
夢見の頻度は性格、体質などの個人の特性に依存する要因と、日常生活の状況、睡眠状態の変化といった状態依存の要因があると考えられる。
夢はレム睡眠中において、多く起こるがノンレム睡眠中にも起こり、特に朝方に多く起こることが分かっている(4)。
この夢見を起こすレム・ノンレム睡眠の発現、生体リズムの変動は健常成人において共通のものであるが、夢を多くみる、みないという違いがどのような原因によるのかは明らかでない。
夢は、日常生活における体験が記憶として保持され、それらの記憶が変化したものが題材となること、または睡眠中には記憶の関連様式が変化することによって奇妙な内容が起こるという説が
報告されている(5)。
また、ストレス、トラウマ体験といった心理的な要因にも影響を受け、海馬機能など、認知機能との関連も指摘されている(6)。
よって、夢の頻度は日常生活における記憶体験の変化、心理的要因、記憶機能の変化などによって変化するものと考えられる。
今後、認知機能やストレスといった心理的要因と夢見頻度との関連を検討することで、夢を作り出すメカニズム、夢をみたと認識する原因の解明の一端を担うことができると考えられる。
文 献
1) 平井富雄「夢の心理学」『睡眠学ハンドブック』
朝倉書店、1994。
2) Ohayon M.M. et al. Prevalence of nightmares
and their relationship to psychopathology and
daytime functioning in insomnia subjects. Sleep
1997; 20:340-348.
3) Diagnostic classification steering committee,
Thorpy, M. J. (Chairman). International
classification of sleep disorders: diagnostic
and coding manual. American Sleep Disorders
Association. 1997
4) Suzuki et al. Dreaming during non-rapid eye
movement sleep in the absence of prior rapid eye
movement sleep. Sleep 2004;27: 1486-90
5) Stickgold et al. Sleep-induced changes
in associative memory. Journal of cognitive
neuroscience 1999;11 :182-93
6) Nielsen et al. What are the memory sources of
dreaming? Nature 2005;437: 1286-9
|