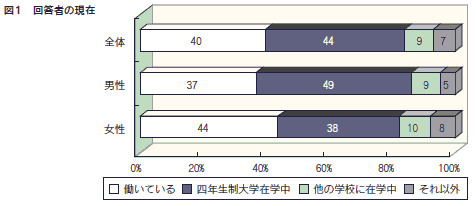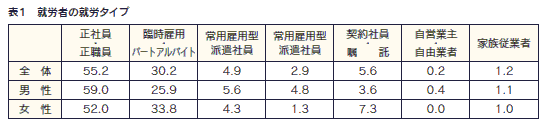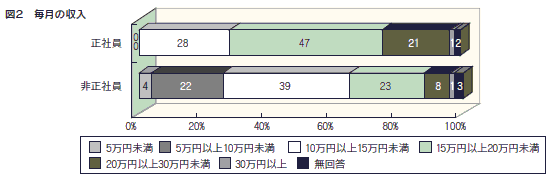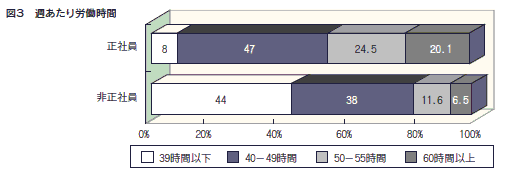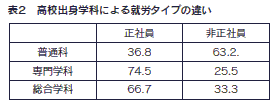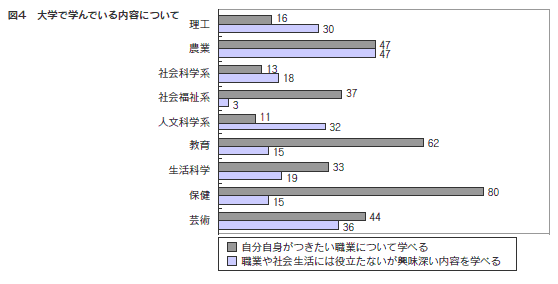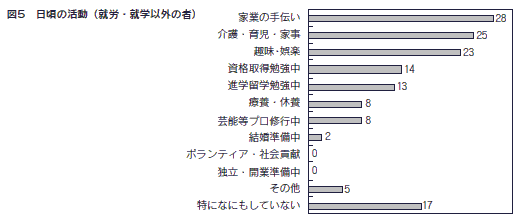■ 若者の教育とキャリア形成に関する調査について
乾 彰夫(首都大学東京)
「若者の教育とキャリア形成に関する調査」は、若者の学校から仕事への移行過程をめぐる今日の状況と課題を明らかにすることを目的に、教育学および教育社会学研究者の共同で進めているものである。若者をめぐる状況が急速に変容する中で、日本教育学会では四年ほど前から、この問題に取り組む特別課題研究プロジェクトがくまれていたが、この研究グループはそれを母体にしている。調査は、2007年4月1日現在二十歳の若者を対象に、その学校から仕事への移行過程および生活と意識の変化の過程を追跡するパネルで、2007年10-12月に第一回調査が行われた。ここでは、調査の概要と第一回調査結果に関する若干の分析を紹介したい。
1.調査の背景と概要
日本の若者の学校から仕事への移行過程は、この十数年の間に劇的に変化した。1990年前後までは、いわゆる新規学卒就職慣行が有効に機能しており、ほぼ八割の若者たちが、新規学卒時に正規雇用就職を果たしていた。しかし90年代に入ってからの若年労働市場の急速な落ち込みの中で正規雇用就職の割合が大きく低下し、学卒直後に非正規雇用(フリーター)や失業を経験する若者たちが急増した。
若者の学校から仕事への移行をめぐる同様の変化は、すでに欧米諸国の多くでは80年代に経験されていた。そこでは学卒直後の失業増などに加え、多くの若者が労働市場の中で安定するようになるまでに、従来に比べ非常に長くの時間を要するようになっていること、また学卒からそこに至るまでの経路が非常に複雑化していることが指摘されてきた。そしてこうした若者たちの直面する困難を子細に明らかにし、有効な若者支援策を策定するために、多くの新たな調査が開始された。その中でも重要な役割を果たしているのが、移行過程を系統的に追跡するパネル調査であった。たとえばイギリスでは、若者の状況変化の顕在化した80年代から、Youth Cohort Study(England and Wales)やScottish School Leavers’Survey(Scotland)が、同一年齢層の約一割前後を対象として現在に至るまでほぼ間断なく実施されている。
学校から仕事への移行が比較的スムーズな段階では、こうしたパネル調査が新たに付け加えることのできる情報は比較的少ない。たとえば80年代までの日本の場合、旧文部省の『学校基本調査』に盛り込まれた「卒業後進路」だけでも、7-8割の若者の移行過程を正確に把握することが可能だった(もちろんたとえば高卒就職者の卒業後3年間の離職率は70-80年代でも40~45パーセント前後であったから、正規就職=安定ということではなかったとしても)。だが90年代半ば以降の若者たちの置かれた状況の下では、ある瞬間だけを切り取った政府の諸統計だけでは、移行過程の実情を浮かび上がらせるにはあまりに情報量が少なくなっていた。
調査を設計するに当たって、私たちはいくつかの問題をまず検討した。一つは年齢、もう一つは方法である。いずれも、対象とする年齢層がもっとも調査対象として把握しづらく、とりわけパネル調査において二年目以降の回答率の確保が難しいということと関係していた。第一の年齢については、学校から仕事への移行ということを考えれば、一番早い若者たちが就職する中卒(15歳)か、少なくとも3割前後が就職する高卒(18歳)を開始年齢とすることが考えられた。しかし約4割を占める四年制大学卒業者が就職をしてある程度落ち着くであろう23-24歳を最終調査時点と想定した場合、調査期間があまりに長期にわたり脱落率が大きくなりすぎると判断した。
第二は調査方法である。一定年齢層の若年者をまとめて把握することが容易にできるのは、いうまでもなく学校経由の調査である。たとえばイギリスの二つの調査は、ともに第一回目は学校経由で行っている。しかしその場合、学校を卒業した二回目調査での脱落率が大きくなる恐れがある。とりわけこの種の調査の認知度がない我が国の場合、その危険性が非常に高いことが考えられた。
以上のような理由から、対象者の選定にあたっては、対象年齢を20歳とした上で、住民基本台帳から抽出し、郵送による質問紙配布・調査員による訪問回収という方法をとることとした。また、若者の置かれている状況や移行過程をめぐって他地域と異なる状況が見られるといわれる沖縄について、全国状況と並行して独自の分析を行うことをめざした。
サンプル抽出は、性別・地域・都市規模を組み合わせた層化二段階無作為抽出法を用いた。第一回調査において沖縄をのぞく全国1250、沖縄250の回答数確保を目標としたが、結果として全国1361、沖縄330の有効回答を得た。なお転居・住所不明をのぞく有効回収率は全国37.7%、沖縄56.0%だった。
以下、第一回調査の結果について若干紹介したい。なお紹介するデータはすべて、沖縄の回答者データについて20歳人口の分布比にあわせたウェイトをかけて集計したものである。
2.第一回調査結果の概要
(1)回答者の現在の状況
回答者の現状は図1の通りである。なお、これを2005年国勢調査の結果と比べると、こちらの女性の在学者比率が若干低くなっているが、国勢調査が 9月30日現在の年齢を基準としているため、そこにはわれわれの調査ではすでに卒業している短大在学者が一定程度含まれているためと考えられる。
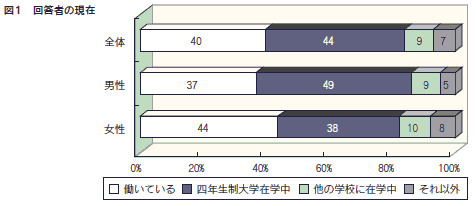
(2)就労者の状況
まず現在すでに就労している若者たち(なお学生については有職の場合もすべて学生として集計)である。表1はその就労タイプごとの分布である。正社員・正職員がかろうじて半数を超えているものの、臨時・パートアルバイトや登録型・日雇型派遣などの不安定就労がかなりの割合を占めている。
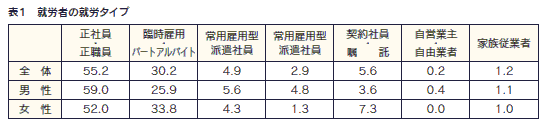
賃金・労働時間について正社員と非正社員に分けて見てみたのが、図2・3である。収入では正社員の場合7割が月15万円以上の収入を得ているのに対し、非正社員では65%が15万円未満である。だがその一方で労働時間をみると、正社員の労働時間の長さが目立つ。正社員の45%が週50時間以上働いており、39時間以下が44%という非正社員とは対照的である。図には示していないが、男性正社員の29%が週60時間以上働いている。この点では図2に示された正社員・非正社員の所得格差のかなりの部分が、賃金単価上の両者の差というよりは労働時間の差によって生じているのかもしれない。
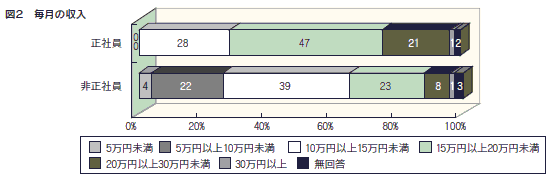
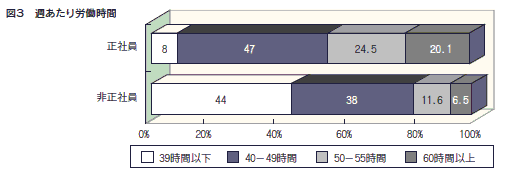
もう一点興味深いのは、高校時の学科が普通科か専門学科かによって現在の就労タイプ(正社員か非正社員か)が大きく分かれていることである。これで見る限り正社員雇用の地位を得るには専門学科卒の方が圧倒的に有利ということになる。もちろん、普通科卒の多数は未だに大学在学中であるため、大卒者が加わったときには、これとはまた異なった様相が示されることであろうが。
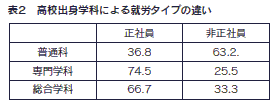
(3)四年制大学在学者
在学者の大多数を占める四年制大学生に、学んでいる内容の意義について尋ねた結果が図4である。保健・教育・社会福祉・生活科学・理工などの分野では、自分がつきたい職業について学べるという見方が、逆に、人文科学系や社会科学系では、職業には関係ないが興味深い内容を学べると感じる者が上回っている。
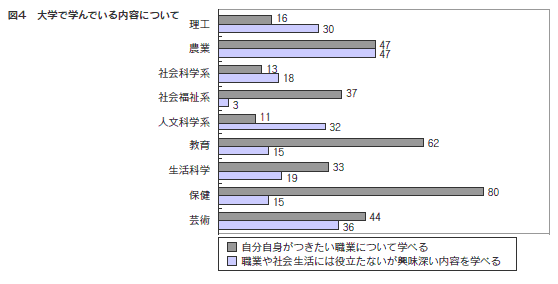
(4)就労・就学以外の者
就労も就学もしていない者は回答者中の約7%をしめた。なおこれは2005年国勢調査結果の20歳人口中の失業者・家事従事者・その他などの合計よりは若干低い値となっている。失業者やその他層は、この種の調査で把握しづらいグループであり、やむを得ないものと考えられる。図5は就労・就学ともしていない者たちの現在の活動等である(複数回答)。なお、これらの者のうち24%が過去一ヶ月の間に求職活動をしており、また32%が求職活動はしなかったものの就職を希望している。就労に消極的な者は半数以下にとどまっている。
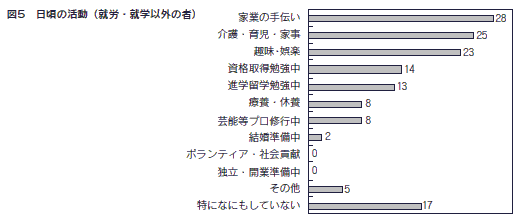
(5)若者たちのもつ社会的ネットワーク
今回の調査では若者たちの自己意識や働くことに関する意識、家族状況など、その生活全般についても質問しているが、ここでは最後に、若者たちのもつネットワークについての結果を紹介しておく。そこでは「遊びなどでいっしょに過ごす」「いっしょにいると安心できる」「今の仕事や学校生活、将来のことについてよく語り合う」「困ったときにアドバイスや情報を提供してくれる」「経済的な面で支えてくれる」について該当する人がいるか、いるとすれば誰かを尋ねた。その結果の第一の特徴は、親の占める比重の高さである。経済的な支えは当然としても、アドバイス、仕事や学校生活、安心など、遊び以外のすべてで親が最も多く選ばれた。第二は、親以外では学校時代の友人の占める比重が大きいことである。学生ばかりでなく、すでに就労している者たちからさえ、仕事や学校、安心などでは以前の学校の友人が現在の職場の同僚等よりもはるかに多く選ばれ、遊びにおいてすら同僚等を上回った。
3.おわりに
以上が、第一回調査の結果についての若干の紹介である。現在、第二回目調査(本年10-11月)と並行しながら、第1回結果についてのさらに詳細な分析を行っている。第1回調査では18歳の4月以降の三ヶ月ごとの主な状況(就学・正規雇用・非正規雇用ほか)についての回答を得ており、過去2年半あまりの状況変化の経過について一定程度把握することが可能であるが、これらも現在分析中である。
はじめに述べたような本調査の目的からすれば、むしろ山場は今後であり、今回協力していただけた回答者の方々の引き続きの協力を願ってやまない。また第一回の実査を担当いただいて目標数以上の回収を実現してくださった中央調査社の皆さんに感謝するとともに今後ともよろしく願いたい所存である。
なお結果概要については、ニューズレター第一号(2008年7月発行、本調査ウェブサイト:http://www.comp.tmu.ac.jp/ycsj2007/reportより質問紙とともにダウンロード可能)に掲載したほか、本年8月に京都・仏教大学で行われた日本教育学会大会において中間報告を行った。報告者は以下の通り。中村髙康(大阪大学)・本田由紀(東京大学)・児島和功(東京都立大学大学院生)・西村貴之(同)・杉田真衣(同)・横井敏郎(北海道大学)・上間陽子(琉球大学)。本稿はニューズレターならびにこれらの報告データをもとにしている。
|